◇手元供養とは?費用相場・種類・方法やメリットと注意点を解説
お墓を維持すること・継承し続けることのハードルが上がった昨今では、手元供養を考える方が増えました。
手元供養では、文字通り手元に遺骨を置いて供養を続けます。
手元供養は一見手軽な方法に思えますが、手元供養ならではのデメリットや注意点があることも知っておかなければいけません。
今回の記事では、手元供養の方法・必要な費用の相場・メリットとデメリットも含めて解説します。
手元供養を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
手元供養とは、文字通り遺骨を自宅に置いて手元で供養することを指します。
手元供養が一般的になった現在では、オブジェのように飾れるミニ骨壷や、遺骨の一部をアクセサリーに加工するサービスも増えています。
これまで、「供養はお墓でするもの」という考えが一般的だった日本で、手元供養や散骨などの供養方法が定着し広がっている理由には、次のようなものがあります。
お墓は先祖代々受け継がれるものですが、少子化が進み親族が一つの地域に集まって暮らす選択をすることが減った今は、お墓の後継者が不足しています。
お墓を管理できる子孫がいなければ、お墓が無縁墓になってしまいます。
お墓の後継者不足は、日本全体で深刻化している問題です。
日本では、祖父母と一緒に暮らす大家族が減り、各家庭が別々に生活する核家族化が進みました。
その結果、若い世代はお墓のある地元とは遠く離れた都市部を生活拠点にするケースが増えています。
お墓参りに何時間もの時間がかかる状態では、お墓を適切に管理することは難しいと言えるでしょう。
お墓を維持するためには、墓地代などを払い続けなければいけません。その負担は後継者のみでなく後継者の子孫にもかかっていくのです。
また、現段階でお墓がない方は、お墓を建てるために100万円以上の費用が必要です。
建墓・お墓の維持にかかるコストは軽いものではないと考えてください。
手元供養と仏壇の違いが分かりにくいと感じる方もいるようですが、手元供養と仏壇の役割は別のものです。
手元供養では、故人の遺骨を中心として自分の望むように故人を供養します。
それに対して仏壇は、宗派の仏様を中心として故人の位牌や仏具を置いてお供物をする供養のスペースです。
それぞれの役割は別のものであるため、仏壇と手元供養を同じ扱いにしないようにしてください。

手元供養は近年人気が高まっている供養の方法ですが、宗教的に・法律的に良いことであるのか不安を感じるという方もいます。
この章では、手元供養についてより詳しく説明しましょう。
「分骨は良くない」「手元供養は良くない」と感じる方もいるようですが、仏教ではお釈迦様の遺骨を弟子8人で分骨したと伝えられているように、分骨や手元供養を悪い行為だと考えていません。
そのため、手元供養は「故人が成仏できない」「縁起が悪い」と考えるのは、間違った解釈だと言えるでしょう。
手元に遺骨を置く行為が法律に反していないのか不安を感じる方もいます。
日本の法律では「墓地、埋葬に関する法律」で、墓地以外に遺骨を埋めることを禁止しています。
しかし、遺骨を手元に残す行為は禁止されていません。
手元供養を選択することで、法律に違反する心配はないのです。

手元供養では、遺骨を自宅に置いて供養を続けます。手元供養を選択するメリットは、次のようなものです。
手元供養自体には別途費用がかかりません。建墓費はもちろん、管理費や維持費を払う必要もないのです。
供養のために費用をかけられないという方でも、手元供養は選択しやすいと言えるでしょう。
手元供養の最大のメリットは、故人を身近に感じられることです。
大切な人との別れが辛い・寂しさを乗り越えられないと感じる方は、手元供養を選ぶと良いでしょう。
手元供養であれば、お墓に行かなくても毎日故人と共に過ごせます。
墓地などの施設を活用した供養では、宗教上・施設上のルールに従わなければいけません。
しかし手元供養にはルールや常識が存在しないため、自分らしい方法で満足がいく供養ができると考えてください。
お供物や個人を想う方法も、自分の心地良いものを選択できます。

手元供養には、メリットのみでなくデメリットもあることを知っておかなければいけません。
この章では、手元供養のデメリットについて説明します。
遺骨は湿気やカビの影響を受けやすいことから、適切に管理しなければいけません。
手元供養した遺骨をただ置いておくだけでは、遺骨にカビが生えててしまう可能性があるのです。
「遺骨はお墓に納めるものだ」と考える親族が現れる可能性がある点も、手元供養のデメリットだと言えるでしょう。
供養に関する考え方は人それぞれです。しかし、親族間のお墓や供養に関係する価値観の違いが、大きな揉め事につながるケースも多いのです。
手元供養をしていた自分が亡くなった場合、親族や自分の子供・孫は両方の遺骨を管理しなければいけなくなります。
手元供養を決める時には、自分に何かあった時の自分の遺骨のみでなく手元供養をしている方の遺骨の扱いについても決めておきましょう。
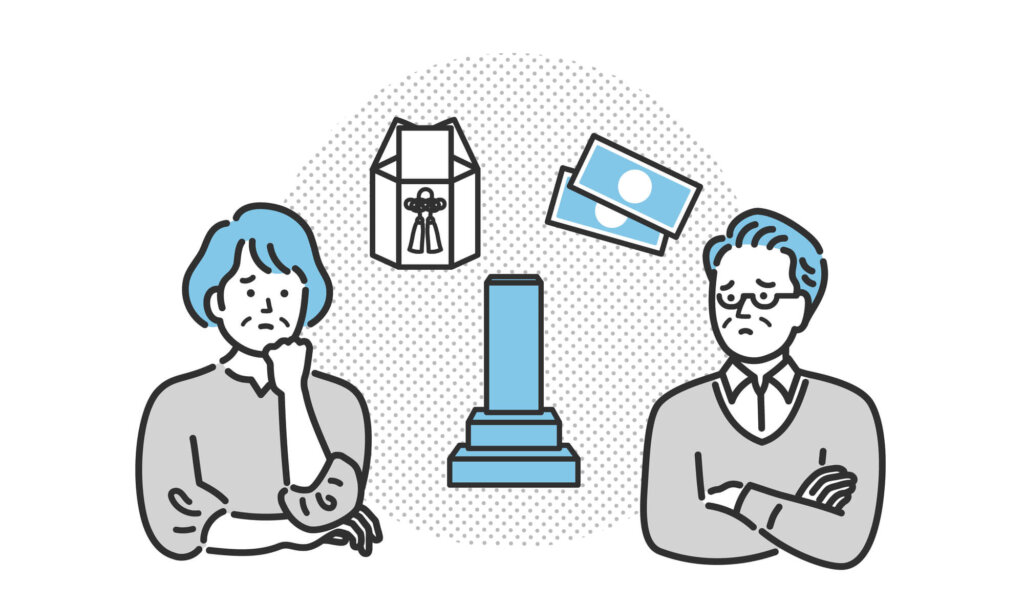
手元供養では、お墓での供養のように建墓費用やお墓の維持費用はかかりません。
しかし、場合によっては以下のような費用が必要になることを知っておきましょう。
手元供養をコンパクトな骨壷で行いたい場合には、骨壷をより小さくするために粉骨作業が必要になります。
粉骨は自分で行っても良いですが、故人の骨を砕く作業は精神的苦痛を伴う上に簡単ではないため、粉骨業者に依頼したほうが良いでしょう。
粉骨にかかる費用の相場は2万円〜3万円程度です。
手元供養する遺骨をおしゃれな骨壷に入れたい・アクセサリーにしたいと考えている方は、加工費用の相場を知っておきましょう。
|
手元供養品 |
加工の費用相場 |
|
アクセサリー |
1万円〜5万円 |
|
ミニ骨壷 |
1万円〜3万円 |
|
写真たて |
1万円〜3万円 |
|
小さなお墓 |
1万円〜10万円 |
手元供養の専門業者であれば、より多種類の加工方法を用意しています。
自分が希望する供養の形に合わせて、最適な手元供養品を選びましょう。
墓じまいをして手元供養をする場合には、手元供養をする遺骨以外の扱いを決めなければいけません。
他の遺骨は永代供養をする・散骨するケースでは、他の遺骨の供養代を計算しておく必要があるでしょう。
また、お墓を閉じる墓じまいにも閉眼供養や墓石の解体費用などがかかります。
閉眼供養のお布施には約5万円〜約10万円、散骨には約10万円〜約50万円の費用が必要です。

手元供養にかかる費用を少しでも抑えたいと考えている方は、次のコツを試してみてください。
先ほどもお伝えしたように、粉骨はプロに任せるべきです。
しかし、粉骨業者では複数のプランを用意しており、立会の場合は追加料金がかかるケースが多いです。
また、手元供養品の製作を依頼する業者に粉骨まで任せることで、セット割引が受けられる可能性もあるでしょう。
粉骨の方法を工夫すれば、粉骨にかかる費用を抑えられます。
ミニ骨壷・写真たてなどの手元供養品は、自分で作ることもできます。相手のことを想いながら考えた手元供養品は、故人を喜ばれるでしょう。
手元供養品は必ずしもプロに頼まなければいけないものではありません。
手元供養をする時には、次の点に注意してください。
以下のポイントは、手元供養のデメリットをカバーする方法でもあります。
遺骨を適切に管理しないと、カビてしまう可能性があります。
特に粉骨済みの遺骨は湿気を含みやすく、カビが発生するリスクが高くなるのです。
このような問題を防ぐために、手元供養では風通しの良い場所に遺骨を置く・遺骨に手で触れないことが大切です。
手元供養のつもりで、自宅の庭に遺骨を埋めてはいけません。
手元供養自体は違法ではありませんが、遺骨を墓地以外の場所に埋めることは日本の法律で禁止されているためです。
庭に手元供養品を置いておくだけで誤解を招く可能性があるため、手元供養は必ず室内で行ってください。

手元供養をしようと決めた時には、次の流れで手元供養を進めてください。
まず、手元供養をしようと考えている方の遺骨を全て手元供養にするのか・分骨して遺骨の一部を手元供養にするのかを決めます。
家族や親族の意見も聞きながら、全員が納得できる方法を選びましょう。
分骨後に手元供養をする場合には、残りの遺骨の納骨先が「分骨証明書」を必要とするか確認します。
分骨証明書は分骨を行った証明になる書類であり、火葬場に依頼することで受け取れます。
火葬後に分骨を決めた場合には、分骨証明書を発行可能な機関を確認してください。
次に、具体的に手元供養をする場所を決めます。
手元供養の保管先に明確なルールはありませんが、遺骨の状態を悪くしないために風通しが良い湿気が少ない場所を選びましょう。
ミニ骨壷やアクセサリーなど、自分が希望する手元供養品を選びます。
手元供養では自宅に遺骨が常に安置されるため、自宅の雰囲気に適したものを選ぶと良いでしょう。
遺骨を身につけたいと考えている方には、アクセサリーをおすすめします。
ここまでの準備が整ってから、手元供養を始めます。
手元供養にルールはありませんが、基本の仏具を準備しても良いでしょう。

お墓を持たない供養の形は、手元供養以外にもあります。
建墓しない・墓じまいをしようと考えている方は、自分たちに適した供養の形について考えてみましょう。
お墓ではなく納骨堂に遺骨を納めて長期的な供養を依頼する方法です。
契約するプランによって、個別に供養をする・合葬する方法を選択できます。
永代供養であれば、半永久的に故人の供養と管理を任せられます。
墓石の代わりに樹木をシンボルとして供養をする方法です。
個別に埋葬する・合葬の2種類があります。
遺骨を粉末状にして海・山などに撒いて供養します。
「死後は自然に還りたい」と考えている方から人気を集めており、散骨後には管理費用などが一切かからないという点もポイントです。
手元供養は現在人気が高まっている供養の方法です。
手元供養であれば、故人を常に身近な存在として感じられることから、大切な人を亡くしてしまった方の心を軽くしてくれるでしょう。
しかし、手元供養にはメリットのみでなくデメリットがある事実も知っておかなければいけません。
この記事を参考に、自分と家族に適した供養の方法は何か考えてみてください。

天井 十秋
10年以上に渡り、全国の海域で散骨を行って参りました。
故人様の旅立ち(エンディング)を「より良く、より自分らしく」をモットーに、1,000名様以上もの供養をサポート。
故人様だけでなく、ご家族様の想いにも寄り添った、散骨プランをご提案いたします。